プレッシャー下でのパフォーマンス発揮と圧倒的ゴール達成をサポートするスポーツメンタルトレーナーの中嶋です!
 おかっぱ
おかっぱ最近、試合で緊張してしまうんだよね。。



試合では誰もが緊張するよね



そんな中でもしっかりと自分らしいパフォーマンスを出していけるように解説していきます!



よろしく!
みなさんは試合で緊張してしまうことはありませんか?



私はめちゃめちゃ緊張してました
- 体の動きが硬くなる
- 頭が真っ白になって冷静な判断ができない
- 体が重くてすぐに疲れてしまう
これらは全て緊張している時の特徴です。
体がこのような状態だと本来自分の持っているパフォーマンスを100%発揮することが難しくなります。
是非とも、この記事を読んでイキイキと自分らしいパフォーマンスを発揮していきましょう!
- 緊張してパフォーマンスが出ない理由が分かる
- 緊張から解き放たれて自分らしいパフォーマンスが出来るようになる
- より競技が楽しくなって、やる気が満ち溢れる



YouTubeでもお話ししています!
中嶋の緊張のストーリー
まず、私の緊張ストーリーをお話しさせてください。
緊張しすぎてパフォーマンスが発揮できなかった10年間
私は高校、大学、社会人(テニスコーチ)と約10年くらい試合で緊張しすぎて、全くパフォーマンスを発揮できませんでした。
特に大学では体育会に所属していたので週6回部活で練習しながらも、試合になると実力の2~30%くらいしか出せない始末。
練習ではできていることが試合になると全くできなくなります。
いつもだったら身体が自動的に動いて勝手にボールを打ってくれる感覚なのに、全く体が言うことを聞かない。
というか、「いつもどう打ってたっけ?」と打ち方が分からなくなる感覚です。
全然ボールに力が伝わらずネットに届かなかったと思ったら、今度は力が入りすぎて「ピョーン」と大きくアウトしたり。
サーブを打つときには「頼むから入ってくれ」と願いながらサーブを打ってました。
当然ながらサーブが入る確率も下がりますし。もし入っても一瞬「ホッ」と安心して、返ってきたリターンに対応が遅れたり。。
そのような断片的なことは憶えているのですが、大学の四年間の試合の記憶もほとんどありません。
それくらい緊張してパニック状態に陥ってたんですね。



これ、マジですから



それは大変ですな
緊張を上手く力に変えてパフォーマンスを発揮できるように!
そんな私でも緊張のメカニズムと対処法を知ることで緊張を力に変えてパフォーマンスを発揮できるようになりました!



本当に!
緊張を力に変えてパフォーマンスを発揮できるようになってからは、見る見るうちに結果も出ましたし、何よりプレーをすることがめちゃめちゃ楽しくなりました!
そして、気づいたのが、縮こまっているときって自分のプレーが出来ていないので、試合をしてもいい課題が見つからないんですよね。
課題が見つからないと練習の目的やモチベーションも薄まりやすいです。
しかし、しっかりとパフォーマンスが発揮した上で負けると、次につながるすごく本質的な課題が見つかります。
試合によって次のレベルに行くための本質的な課題が見つかると、練習に目的意識が生まれ、モチベーションが高まり、集中力が上がります。
是非とも、この良いサイクルをみなさんにも作っていただきたいですね!



そのサイクルに入りたい!



それでは次は緊張のメカニズムについて説明していきます!
緊張のメカニズム
緊張を克服するにはまずは緊張のメカニズムを抑えておくのが大事ですね!
ちなみに、あなたはなぜ人が緊張するかご存じですか?



え?なんで緊張するの?



実は私たちがサルだった頃の防衛本能の名残なんです!



さ、サル?!!
防衛本能??!
そう、人間がよりサルに近かった原始時代、我々は弱肉強食の世界に生きていました。




ライオンやトラなど、強い捕食動物から生き延びることが我々の何よりの優先順位ダントツ1位。
生き延びるために自分を守る機能が防衛本能です。
その防衛本能の名残りが「緊張反応」として今でも残っているのですね。
次はその緊張反応について解説していきます。
防衛本能である緊張反応の代表例6つ



防衛本能である緊張反応の代表例は6つあります!
緊張反応①ソワソワ


緊張するとソワソワ落ち着かなくなることはありませんか?
ソワソワするのは、警戒心を強く持ってる証拠ですね。
なぜなら、「ボケ~っ」としていると捕食動物に「ガブツ!」と殺られます。
なので、常にソワソワと周りを警戒しながら、いざという時に備えなければなりません。
緊張反応②ドキドキ
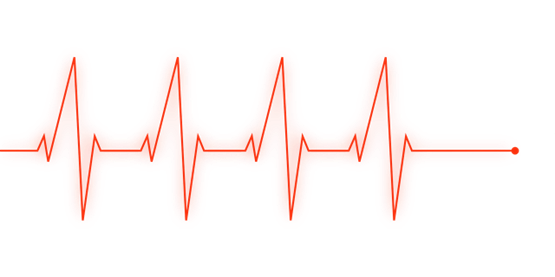

緊張反応として分かりやすいのが心臓のドキドキ。
自分の心臓の音が聞こえるくらいドックンドックンと心臓が脈打つ方もおられると思います。
これは、敵に遭遇した時に心臓を力強く動かすことで血流を流し、動きのパフォーマンスを上げることに繋がります。
ワンピースのルフィの「ギア2」みたいな感じですね!
緊張反応③頭が真っ白になる


授業やセミナーで急に当てられて頭が真っ白になったことはありませんか?
敵に襲われそうになった時にはイチイチ深く考察している時間はありません。
闘うか?逃げるか?
「fight or flight」
選択はふたつに1つ。
素早く反射的に行動を取るためにも頭が真っ白になる方が都合が良かったのですね。
緊張反応④発汗


「冷や汗」や「手に汗握る」とも言いますが、緊張すると発汗します。
これは手に汗をかくことで手を湿らせ、岩や木をつたって逃げやすくするためです。
緊張反応⑤鳥肌


人間だとあまり実感しませんが、鳥肌は動物が威嚇する時に身体を大きく見せる機能です。
猫が「シャー!!」と威嚇する時も身体を上に大きくし、毛を逆立てて出来る限り大きく見せます。
もっとも分かりやすいのはハリネズミですね。
毛を逆立てることで身体を大きく見せ、あわよくば相手にビビって逃げてもらおうという魂胆です。
緊張反応⑥身体の硬直


硬直はスポーツで身体が固まってしまうような現象です。
スポーツにおいてはこの硬直がなかなか厄介ですが。
これは敵の鋭い爪で引っかかれたり、牙で噛みつかれたりしたときに、身体を硬直させることで防御力を上げようとする機能です。
緊張反応は生き延びるのに必要な機能だった
このように緊張反応は原始時代には我々が生き延びることに大きく貢献してくれました。
むしろ緊張するからこそ生き延びているのですね。



逆にメンタル強い
しかし!
現代では少し話が変わってきます。
逃げて生き延びるのが最優先だった原始時代とは違い、今は
- プロスポーツでは、自分らしいプレーをし、成績を出すこと
- 良い学校に入るには、試験でパニックを起こさずに頭を働かせて問題を解くこと
- 会社から評価されるには、プレゼンでバッチリと説明し、商談を成功させること
これらが、より良く生きるための生存戦略として求められる要素になってきています。
このような現代の環境下では強すぎる緊張反応はどうしても邪魔になってしまうのですね。



ガーン
緊張反応のスイッチはマイナス感情


では、強すぎる緊張反応を起こさない為にはどうすればいいか?
ここで押さえておきたいのが緊張反応のスイッチが何なのか?ということ。
スイッチさえ分かっていれば対策も立てやすいですよね。
実は緊張反応のスイッチは
マイナス感情
なんです。
つまり、
不安、焦り、恐怖、劣等感、羞恥心、などなど
マイナス感情が緊張反応を引き起こすスイッチになっています。
逆を言えば、無駄にマイナス感情を誘発しないような思考の転換ができると緊張反応を抑えることが出来るのですね!
プレッシャーが大きいほど緊張も強くなる
当然ながら、プレッシャーが大きくなるほど緊張も大きくなります。
1つ例え話をしましょう。
平均台を渡れますか?
想像してください。
あなたの目の前に高さ50cm、幅20cm、長さ5mの平均台があります。
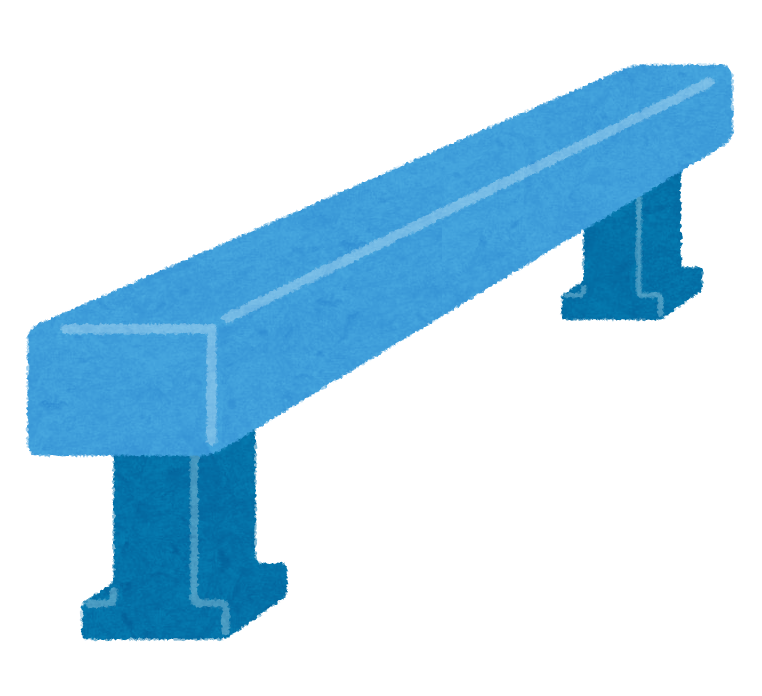

その平均台を渡ることは簡単ですか?
恐らく、ほとんどの人が「簡単だ」と答えると思います。



「難しい」と思ってしまった方、、なんかゴメンナサイ。笑
では、質問を変えます。
同じく高さ50cm、幅20cm、長さ5mの平均台があります。
この平均台を高さ200mのビルとビルの間に置いたとします。
遥か下には自動車や通行人が豆粒のように見え、もし足を滑らせたら100%死ぬ状況。
あなたはこの平均台を渡れますか?


、、どうでしょう?
「難しい」と答える方がかなり増えるのではないでしょうか?



ちなみに、私も間違いなく「難しい」と答えます。



だって恐いもん。



コラ
今回は大袈裟に例を挙げましたが、試合中にこれと同じことが起こっているんですね。
要は、大事な試合になればなるほど負けることを異常に恐れて、
『いつもなら簡単なことを、とてつもなく難しいことに感じさせてしまっている』
ってことを何となく掴んでいただければOKです!



めっちゃある
試合での緊張を克服方法①ミスを恐れるのではなく、今ここに集中



それでは、試合での緊張の克服方法を解説していきます!
今、その瞬間のプレーに集中する
結論から言います。
『どれだけ、今その瞬間のプレーに集中出来ているか?』
が大事です。
言うが易しとは良く言ったもので、「それが難しいんだ!」って声が聞こえてきそうですね。笑
メンタルトレーニングでの試合でのパフォーマンス発揮に関しては究極的にここに向かっていけるように様々な角度からアプローチをしていきます。
今回、説明していきたいことは、本来同じことをするにしても状況によって難易度が変わるということ。
テニスの場合
例えばテニスの
・練習をしててミスを気にせずバコバコと気持ち良くボールを打っている時。(ノビノビ)
・すごく大事な試合で5-5のデュースの時。(緊張)
何かやることって違います?
その瞬間にやることって何ですか?
『ボールを追いかけて打つ』
以上!
そうです、極論やることは一緒なんです。
とってもシンプル。
じゃ、何が違うのか?
それは失うもの(失うと思ってしまっているもの)の大きさです。
試合での緊張の克服方法➁相手を特徴で捉え、プレーを決める
試合中に何が起こっているかは分かった。
簡単なことを勝手に難しい状況下に感じてしまっていることは分かった。
で、じゃどうするか?
『どれだけ、今、その瞬間のプレーに集中できるか』
って所に話を戻しましょう。
格下格上の概念を横に置いておく
今回は格下に負けることにプレッシャーを感じ緊張してしまうという前提で話しましょう。
ここのプレッシャーや緊張をクリアにしていくのにも色んな方法がありますが、1つ紹介します。
それは格上格下の概念を横に置いておくということ。
そもそも、格上格下って概念が余計です。
いらなくないですか?格上格下って。
ちなみに、みなさんは格上格下って何で判断していますか?
プレッシャーを受けやすいという方が陥りやすいのはただただランキングや戦績で判断してしまうというパターン。
ランキングで相手を判断した場合、見てるのはただの数字であって、相手本人ではありません。
ここで大事なことは“相手がどんな選手なのかを分析する”ということ。
「ランキングが高いから強いだろう」
「ランキングが低いから弱いだろう」
この状態って相手の何が分かってますか?
何も分かってないですよね。
基本的に対人スポーツでは相手によって戦術を多少なり変えざるを得ないのですが、戦い方を考察する際に大事なのは相手の情報です。
・どんなプレースタイルか?
・どんなパターンやショットが得意か?
・どんなパターンやショットが苦手か?
・相手は自分よりどの要素で上回っているか?
・自分は相手よりどの要素で上回っているか?
・どんなクセがあるか?
etc、、
それに対して“自分がどんな戦い方をしたら勝てる可能性が上がるのか”を考えていきたいですよね。
ランキングで相手を判断することは真っ白な霧の中で訳も分からず相手と戦っているようなもの。
ただただ、謎の不安に襲われています。
けど、視界が開けて相手がしっかり見えたらどうでしょう?
不必要な不安はなくなり、今やるべきことが見えてくるハズ。
自分の得意なパターンを貫くべきか、相手の弱点に合わせるのか、、そこの選択肢に正解は無く、その時次第ですが、考える発想を持つことが出来ます。
で、こんな風に相手選手の特徴を挙げていくとどうでしょう?
試合をしてる瞬間、格上、格下って感覚はどっちでも良くないですか?
試合をしている瞬間、ランキングが上下ってどっちでも良くないですか?
試合をしている瞬間、対戦成績に対して何回勝ってて、何回負けてるかってどっちでも良くないですか?
今、考えるべきなのは
“その選手がどんな選手か?”
“ その相手に対してどう戦っていくか?”
という部分だけです。
そうやって“どう戦っていくか?”にフォーカスすることで何が起こるか?
やるべきことに集中しやすくなるんです。
今、この瞬間に集中しやすくなるんです。
相手を分析し、自分がどんなプレーをすること重要かってことにフォーカスすることが結果的にプレーへの深い集中状態を作りやすくなるんですね!
格上、格下に対してプレッシャーを受けやすいな、、という方は是非、プレーに集中する状態を作るためにも格上、格下という概念よりも“相手がどんな選手か?”をできるだけ具体的に探り、“じゃ、自分はどんなプレーをするか?”に目を向けることにトライしてみてください!
そして、そのような戦い方をした上で負けた場合、それはただの負けではなく、それは
“次の勝利への第一歩”。
試合の中で得ることはたくさんあったはずなので、それを次に活かす行動をまた考えていきましょう。
まとめ
・スポーツでは格上、格下と格付けされ、格上が優勢とされる。
・だからこそ、格下選手と対戦する時に、必要以上にプレッシャーを感じ、緊張してしまう選手は少なくない。
・その中でも本来のパフォーマンスを出し切るには『 その瞬間に集中していること』が大事。
・しかし、試合の中や、もしくは“ 平均台を渡る”など、同じ行動をするにしてもその時の状況の捉え方で難易度は変わってくる。
・そのような周囲の状況にとらわれずに本来の自分の実力を出し切るために、格上、格下という虚像の相手にとらわれずに、目の前にいる選手がどんな選手で、その選手に勝つためにはどんなプレーをしていきたいか?に目を向け、ゲームに集中していくことに繋げていきたい。
以上、スポーツの試合で起こる緊張について考えてみた記事でした!
【チェック!】緊張の記事はコチラも参考にしてみてください!





緊張についてもう少し深ぼってしっかりクリアにしていきたい方は下記の体験セッションを受けてみてください!
1on1体験セッションを受ける



1on1メンタルセッションを特別価格で体験できます!


1on1体験メンタルセッション
時間:75分間
特別価格:5,500円(税込み)
無料体験キャンペーン中!
形式:Zoomもしくは対面
※対面の場合はレンタルルームの費用(約1,000円)の負担をお願いいたします。


体験チームメンタルセッションを受ける



100チームに到達するまで体験無料です!
100チームメンタルセッションチャレンジ開催中!
時間:90~120分
期間限定:無料!
形式:Zoomもしくは対面
※対面の場合は場所の確保と交通費のご負担をよろしくお願いします。





100チームメンタルトレーニングチャレンジの詳しい内容はコチラから


LINE登録
ライン公式アカウントからブログの更新情報を受け取ることが出来ます!
体験メンタルトレーニング、チームメンタルトレーニングもラインからでも受付可能です!



















